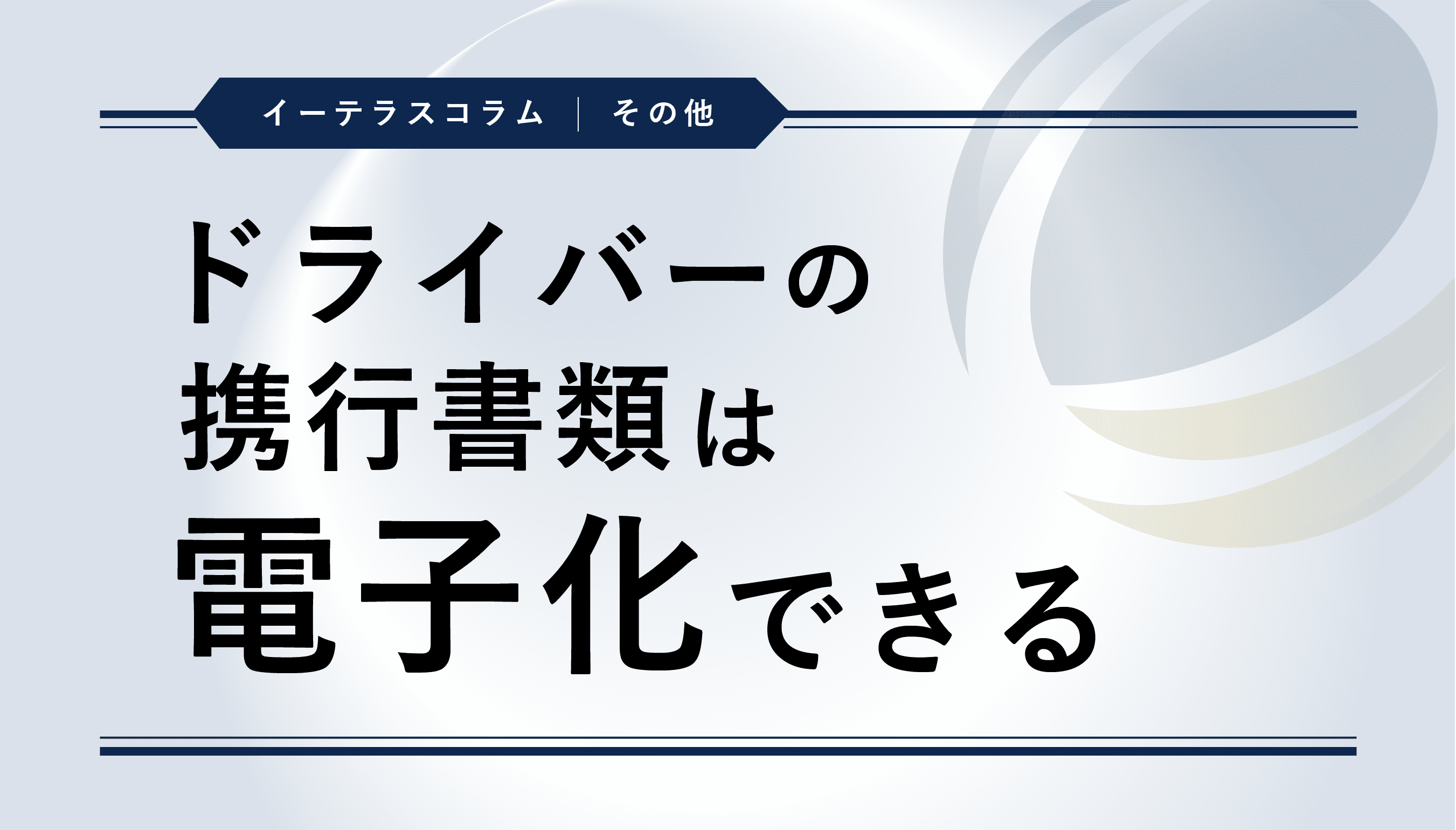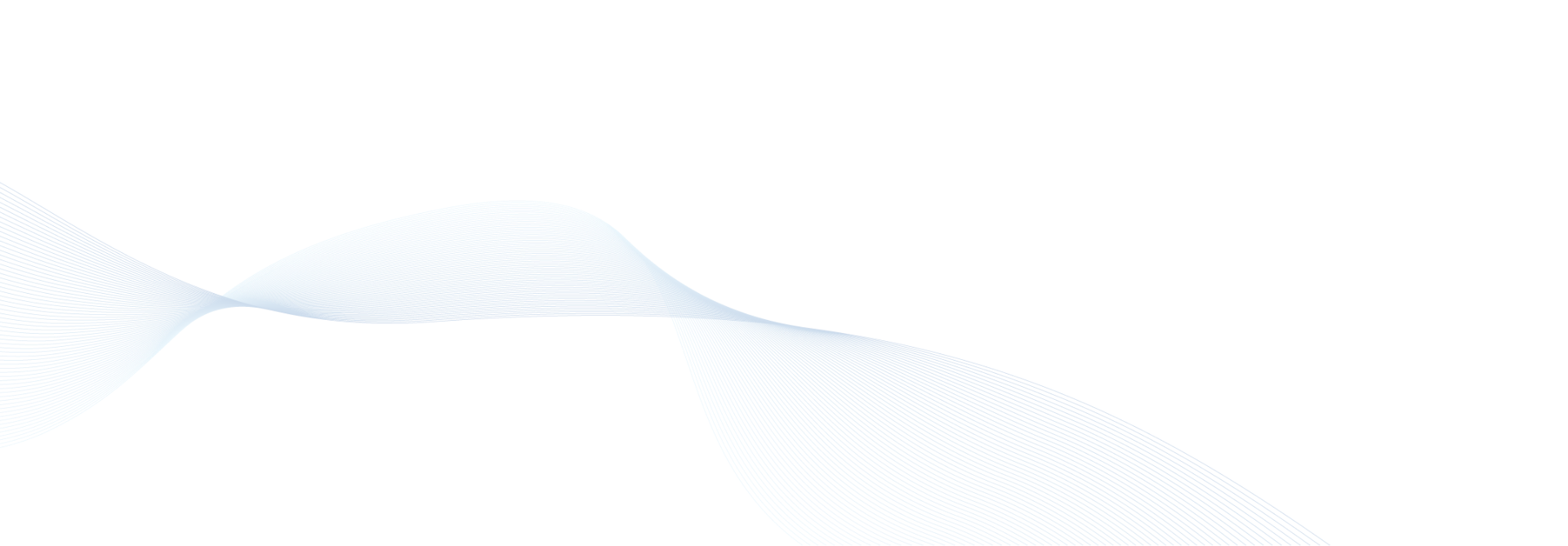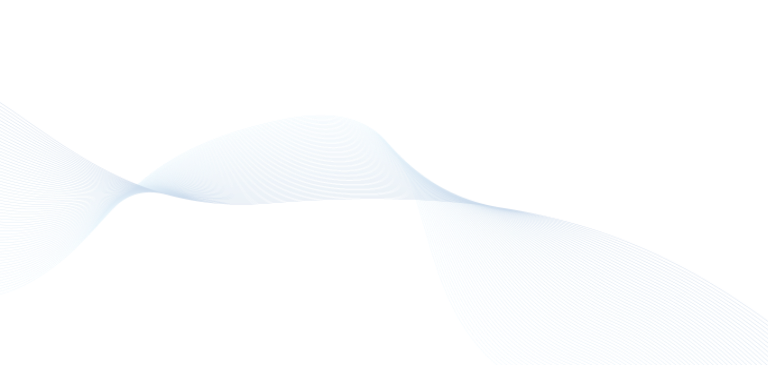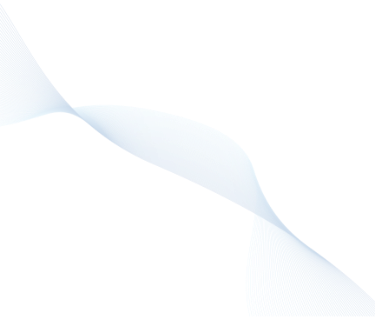.png)



COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
有価物?それとも廃棄物?現場で迷ったときの判断ポイントとは
「これは有価物ですか?それとも廃棄物?」
お客様からこうしたご相談を受けることはありませんか?一見すると単純な問いに思えるかもしれませんが、実際には判断が難しいケースも多くあります。
その理由の一つが「有価物かどうか」を明確に決定づける基準が存在しないことです。実務では「総合判断説」と呼ばれる考え方を使って判断される場面がありますが、これは“判断のための指針”であり、絶対的な基準ではありません。
今回は、現場で迷いがちな「有価物と廃棄物の線引き」について、整理してみたいと思います。
「総合判断説」って何のこと?
先ほどご紹介した「総合判断説」とはそもそも、どういった内容なのでしょうか?
これは、平成25年3月29日環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」で「本来廃棄物であるはずのものが有価物と称して法の規制を免れようとする事例が後を絶たないことから、総合的に判断するための要素」として「総合判断説」が通知されました。
有価物は有価物となった時点で、原則として廃棄物処理法の適用を受けません。自己申告で「これは有価物です」と言っておきながら、その実態は廃棄物として不適正に処理されていた…という脱法行為が後を立たず、その対策として「総合判断」の基準が生まれたというわけですね。
通知のタイトルも「行政処分の指針について」ですから、この基準で行政処分しますよ!という…なかなか厳しい内容です。
そのため、有価物として認められれば廃棄物処理法の規制を受けなくなる一方で、不適正な処理を避けるため、この判断には慎重さが求められるということがお分かりいただけると思います。
では、総合判断説を詳しくみていきましょう。総合判断説は5つの要素で構成されています。
総合判断説はそれぞれの要素の頭に「売り物なんだから」と付け加えて読むと、分かりやすくなります。
例えば「物の性状」であれば「売り物なのだから、品質が一定以上で、飛散・流出・悪臭があってはならない」といった具合です。
このように「売り物」として考えれば“当たり前のこと”を 5つの視点で押さえることが大切です。
ここで注意したいのが「5つの条件をすべて満たしたからといって有価物と断定できるわけではない」ということです。逆に、1つでも該当しなかったからといって、即座に廃棄物になるわけでもありません。
この判断基準はあくまで「総合的な要素」を提示しているに過ぎません。
そのため、どんなにこの基準を読み込んでも、最終的な判断はケースバイケースになるのです。
では、なぜこのように“曖昧な基準”しか存在しないのでしょうか?
それは判断基準をあえて曖昧にすることで、抜け道を作らない仕組みにしているからです。抜け道ができてしまうと、都合よく解釈して不適正処理につながる恐れもあります。
怪しい事案があれば、何かしらの理由で廃棄物として認定できるようにあえて曖昧な基準にしているのです。
当てはまるものを有価物と認めるのではなく、怪しいケースにおいて、5つの基準のどれかを理由にしてNGにできる…と考えておくと良いでしょう。
では、こんな曖昧な基準の中で、実際にどのように判断すればよいのか?を考えていきましょう。
【ケーススタディ①】金属スクラップの取り扱い
金属スクラップを買い取ってもらう場合はどうでしょうか?金属スクラップは一般的に有価物として買い取られるケースが多く、製品として市場が成立しています。金属スクラップの買い取りを専門にしている業者も多く存在します。もちろん運搬費の方が高くなってしまう場合は逆有償として扱わなければいけませんが、売却して純粋に利益が出ていれば有価物として認識することに問題ありません。
(逆有償の詳細についてはこちら:「逆有償とは?既存取引がいつの間にか法律違反に!」)
今回のように有価物であることが明らかな場合は、総合判断説の要素を確認する必要はないかもしれませんね。
では、次のケースはどうでしょうか?
【ケーススタディ②】貴金属含有の有害汚泥
今までは廃棄物だったものを、有価物として売却したいという場合はどうでしょうか。
貴金属が含まれる汚泥ですが、有害物質も含まれるようです。
この場合…
・貴金属の含有率に本当の価値があるか?
・有害物質の適切な処理ができるか?
・処理残渣の対応コストは?
など、様々な懸念が浮かびます。
このように、本当に有価物?と迷うものは、総合判断説の要素を参考にして、慎重に判断しましょう。
場合によっては、管轄行政に問い合わせて、見解を示してもらう必要があるかもしれません。
“迷ったら廃棄物として扱う”のが基本方針
いかがでしたでしょうか?
有価物か廃棄物か——その境界線は非常に曖昧で、必ずしも明確な答えが存在するとは限りません。「総合判断説」は、その曖昧さを前提に、不適切な処理を防ぐための“判断の視点”を与えてくれるものにすぎません。明確な有価性がある場合は問題ありませんが、少しでも迷いが生じたときには「グレーなものは廃棄物として扱う」姿勢がトラブルや万が一の法令違反の回避につながります。
法的なリスクを未然に防ぐためにも、“何を根拠にどう判断したのか”を社内で共有し、判断の透明性を高めていきましょう。

執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。
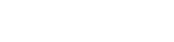


.png)