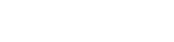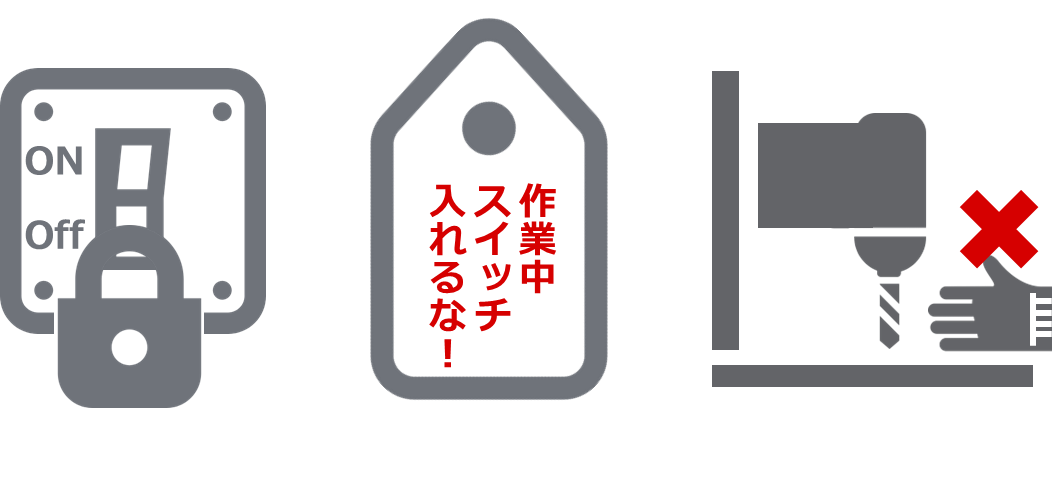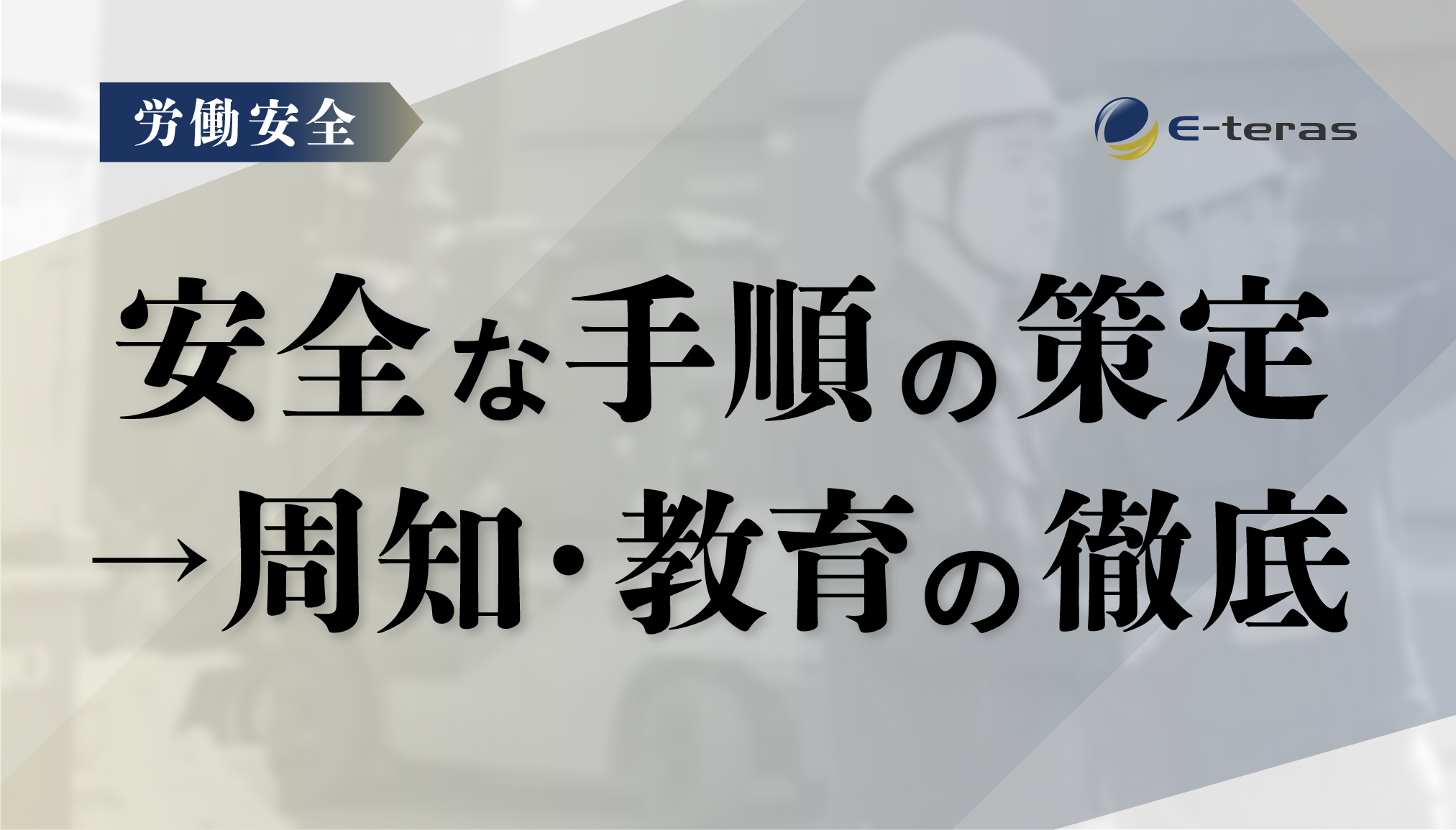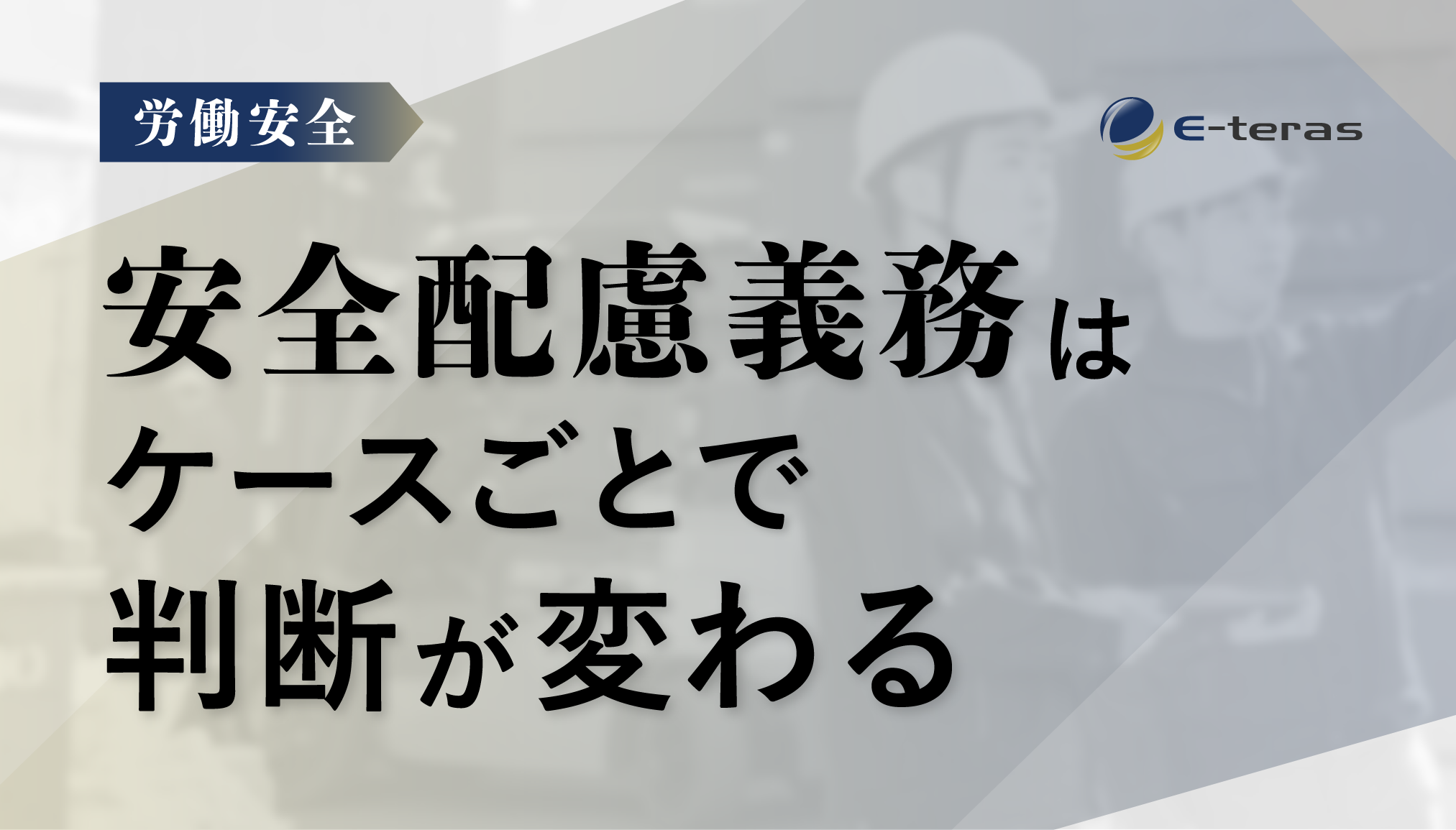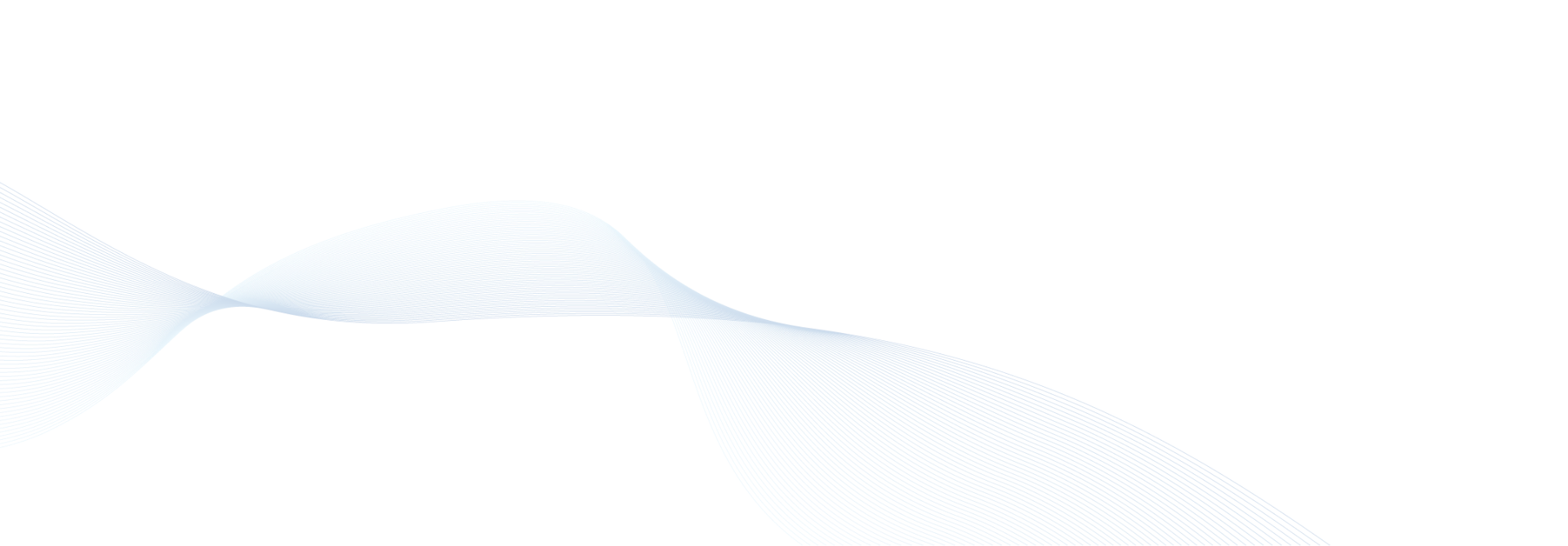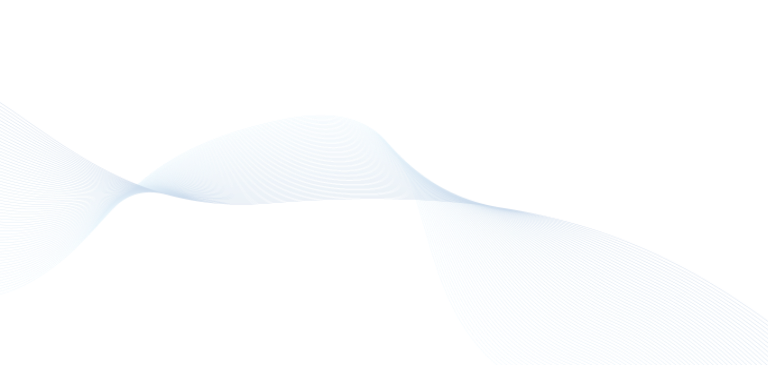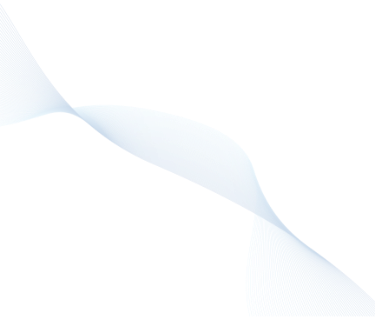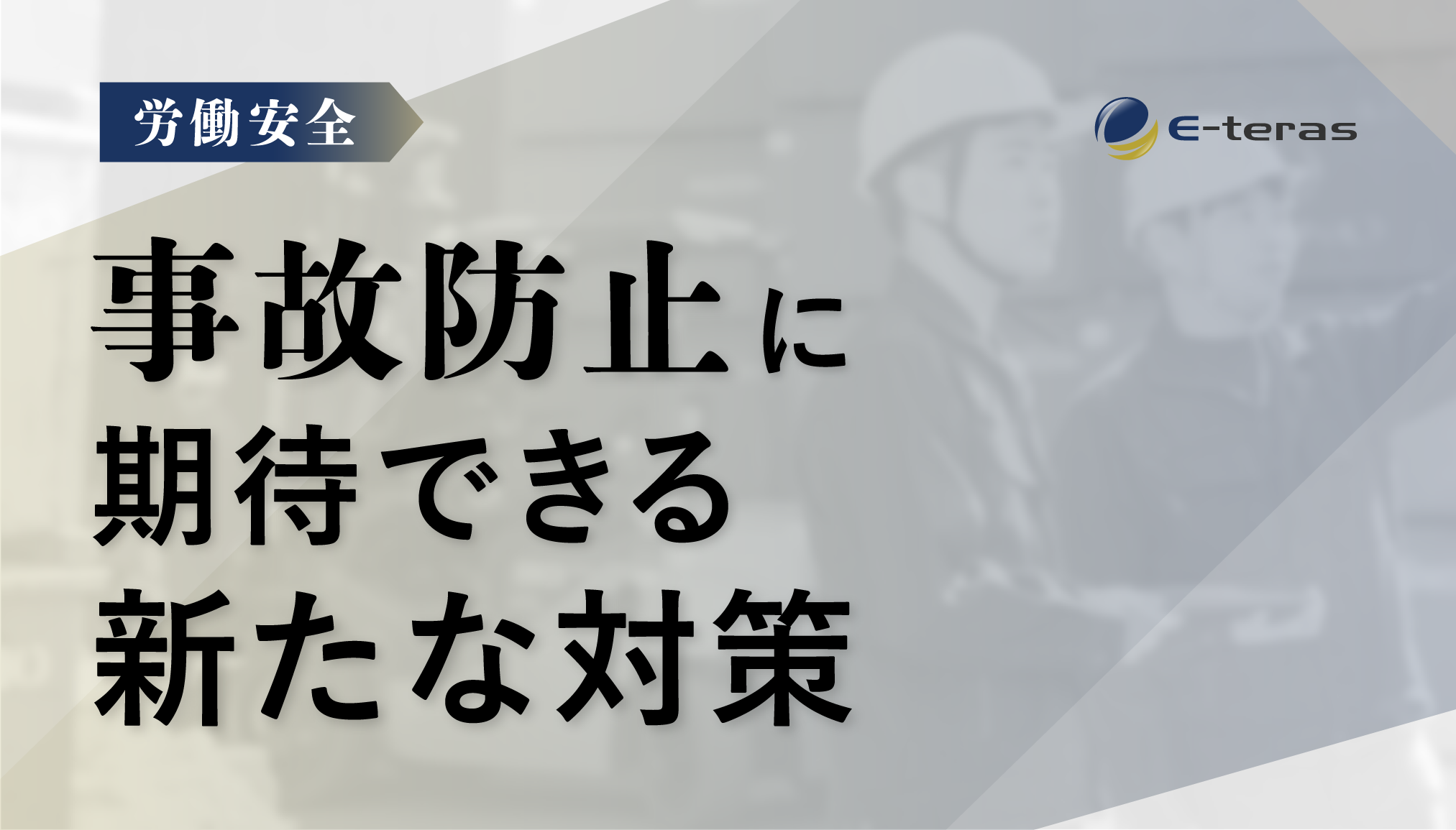



COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
事業者が把握しておくべき『安全配慮義務』とは
安全配慮義務という言葉はよく耳にしますが、いざ具体的に説明するとなると難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。これは安全配慮義務の範囲が非常に広く、明確にしづらい概念だからです。
今回は、安全配慮義務とは何かという基本に立ち返り、現場で役立つよう、具体例を交えて分かりやすく解説します。
安全配慮義務の定義
安全配慮義務とは、主に以下の2つの法律条文で定義されています。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
労働安全衛生法3条1項
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない
どちらも、労働者の生命や身体の安全を確保するために、事業者が必要な配慮を行うべきだと明記されています。
今回は、事故による労働災害を主な対象として掘り下げて考えます。
まず注目するのは、労働安全衛生法3条1項の条文中にある
という部分です。この法律では機械の使用、作業、化学薬品の取り扱いなどについて安全基準を設けています。しかし、それらはあくまで「最低基準」であり、事業者に各職場の状況に合わせてさらに多くの安全配慮と責任が求められています。
しかもまた、安全配慮義務の対象は機械や薬品などによる事故だけでなく、長時間労働による健康被害やメンタルヘルス、さらにはハラスメントによる被害まで幅広く含まれる点にも注意が必要です。
労働災害を防止するための基準
例えば、機械を使用して作業を行う際には、大きく2種類の安全基準が存在します。1つは、すべての機械設備に共通して適用される「一般基準」、もう1つは特定の機械や装置に適用される「種類別安全基準」です。
一般基準
「一般基準」とは、機械の回転軸や歯車など、労働者が巻き込まれたり挟まれたりする危険がある部分に安全カバーや囲い、スリーブなどの保護設備を設ける基準のことです。こうした設備は、労働災害を未然に防ぐための重要な安全対策として義務付けられています。
また、機械の運転を開始する前には周囲に合図を送り、安全を確認することが義務付けられています。メンテナンス作業の際には必ず機械を停止し、誤作動を防ぐためにロックアウトや札掛けといった措置を行う必要があります。
さらに、作業時の服装についてもルールがあり、作業服や作業帽、適切な手袋を着用することが基本ですが、回転体に手が巻き込まれる危険がある作業では、手袋の着用が禁止される場合もあるので注意が必要です。(図1)。
種類別安全基準
「種類別安全基準」とは、機械ごとの特有な危険性に合わせて設定される安全基準のことです。例えば、遠心装置では蓋を設置する、大型の粉砕機では作業者が開口部から転落するリスクがあるため囲いや柵を設置するなど、機械の種類や作業状況に応じた具体的な安全対策が求められます。これにより個別の危険にしっかりと対応し、労働者の安全を守っています。
化学物質の安全配慮義務
化学物質を扱う際の安全配慮としては、SDS(安全データシート)の備え付け・掲示、保護具の適切な使用などが基本となります。ただし、これらを守るだけでなく、対象物質ごとのリスクアセスメントを法律で実施する義務があります。リスクアセスメントによって潜在的な危険性を評価し、具体的な対策を講じることが職場の安全管理を進める上で重要です。
リスクアセスメントは、SDS交付対象の化学物質ごとに必ず実施が義務付けられており、最近の法改正で記録の保存も求められるようになりました。この取り組みによって、各化学物質の危険性を事前に把握し、職場で具体的かつ適切な安全対策を行うことが可能になります。
リスクアセスメントを怠って事故が起きた場合「安全配慮義務違反」と判断される可能性があります。また、リスクアセスメントを実施していても、不十分な内容だったり、記録が適切に保存されていない場合も同様に責任を問われるリスクがあります。化学物質のリスクを事前に評価し、必要な安全対策を講じることは企業の重要な責任であり、これを怠ると重大な過失とみなされる可能性があるため注意が必要です。

執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。