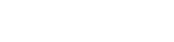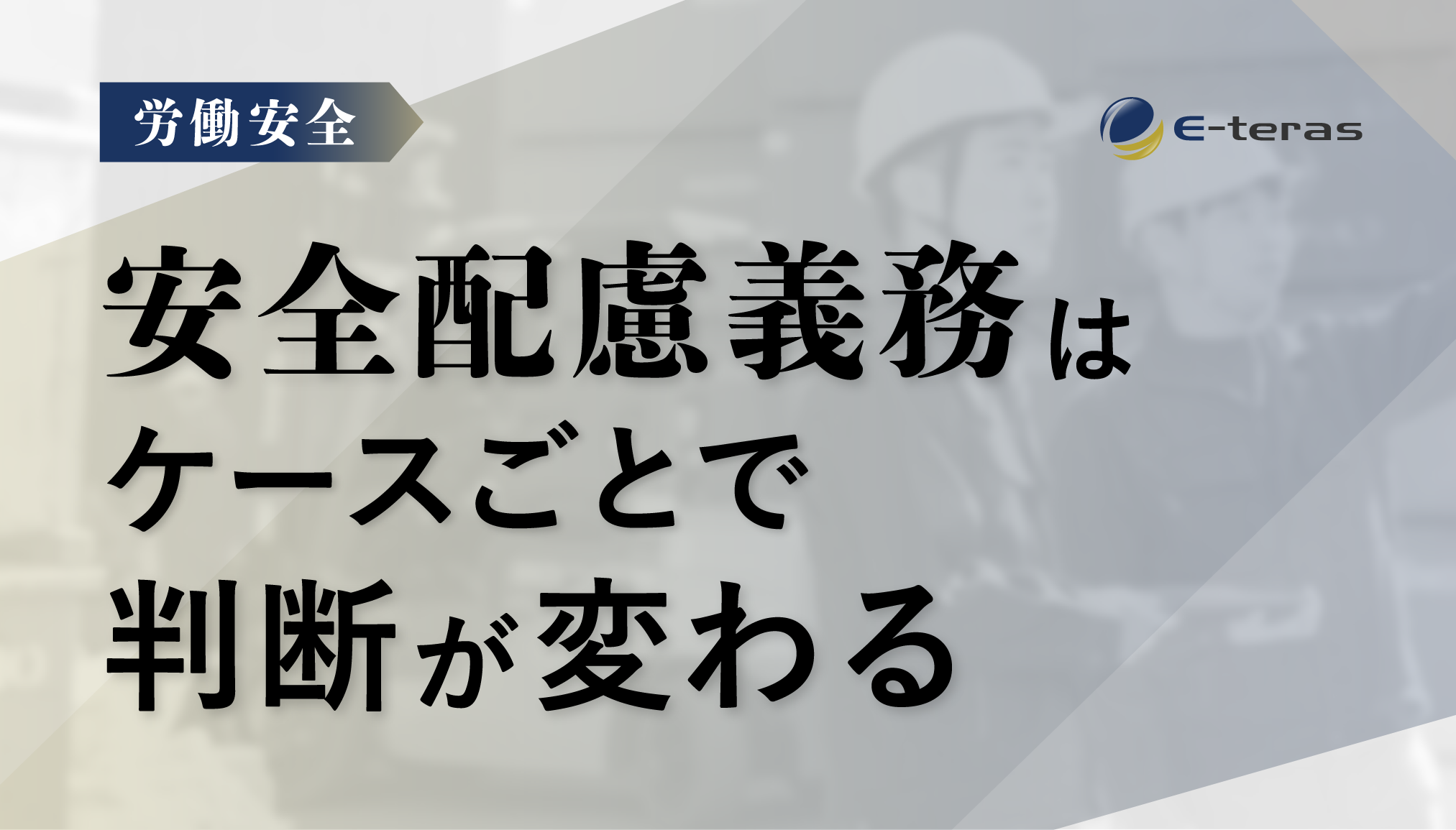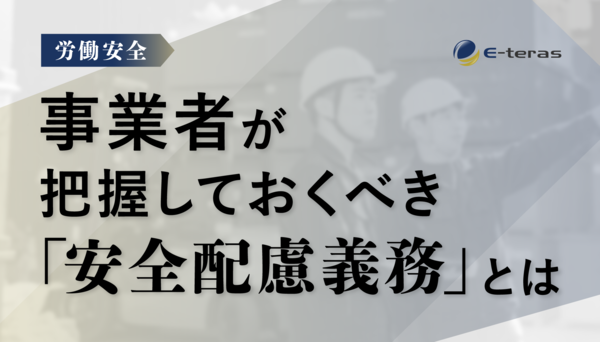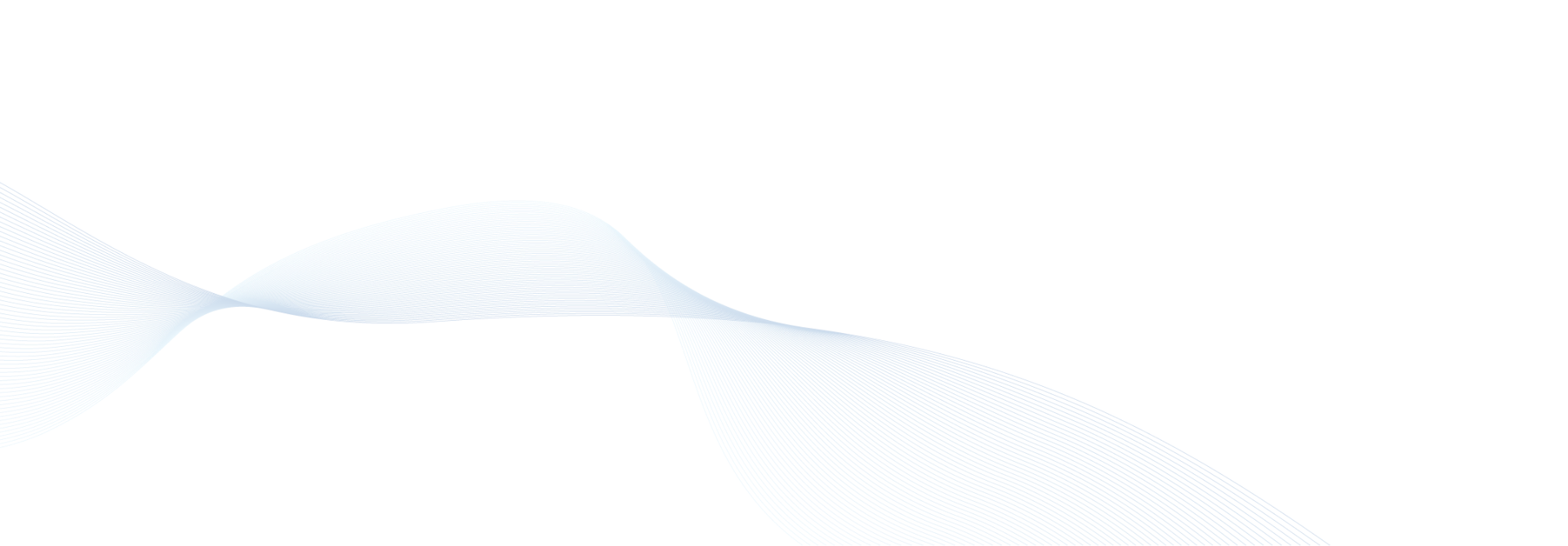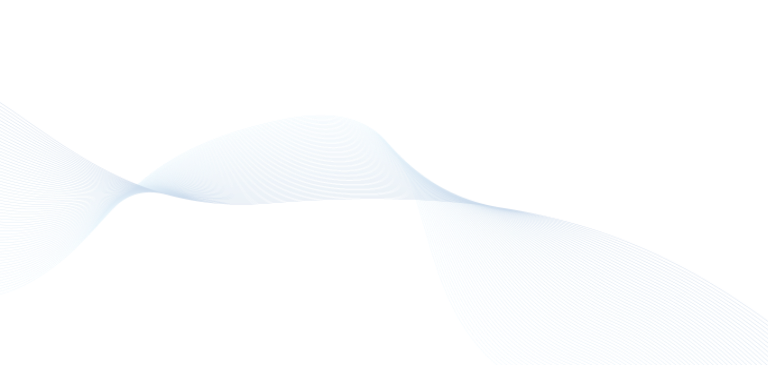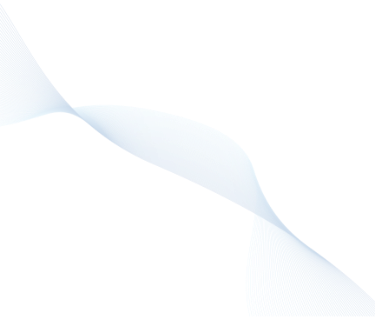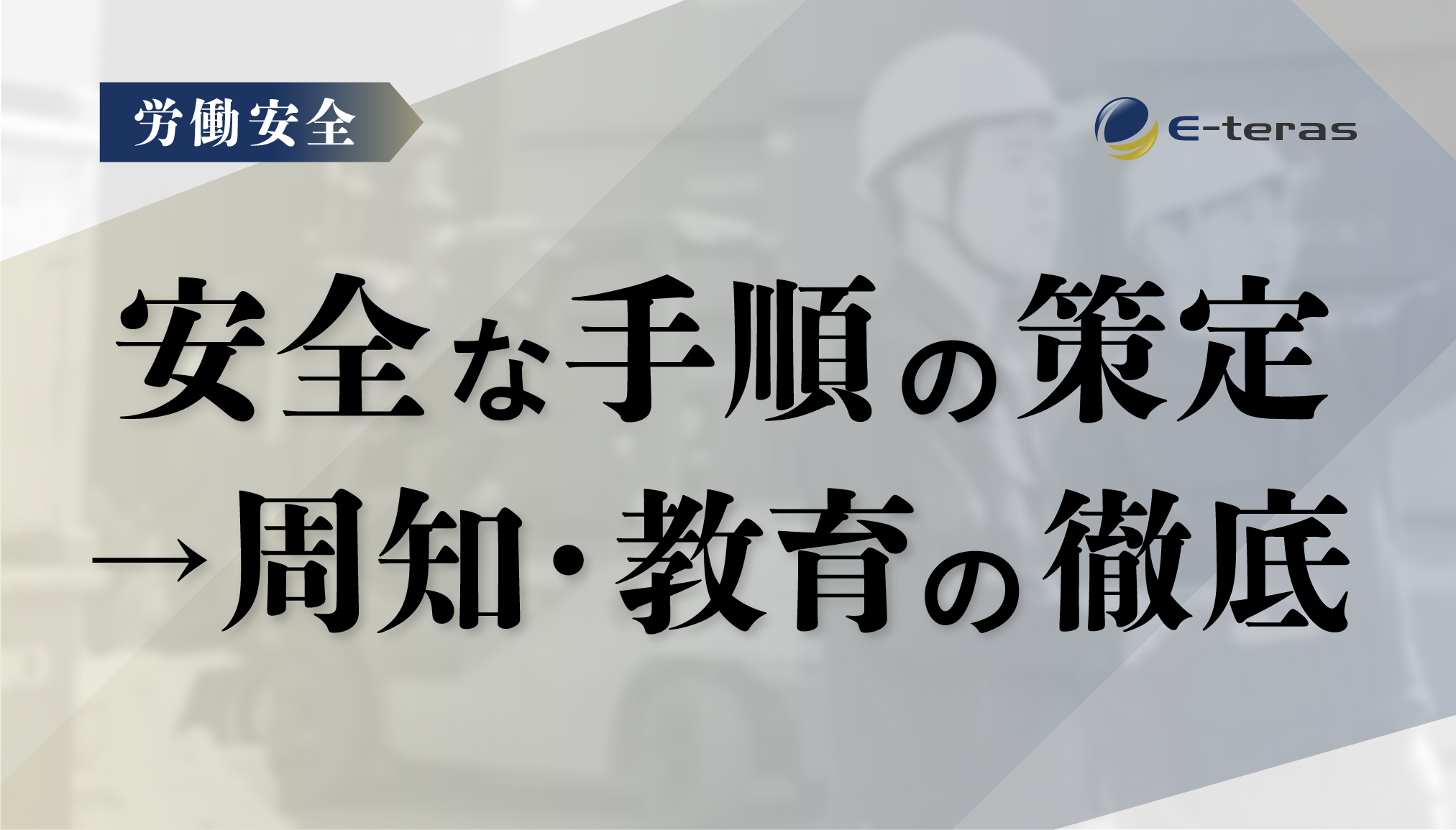



COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
事故防止に期待できる新たな対策
前回までの解説では、安全配慮義務の厳しさと、徹底することの難しさについてお伝えしてきました。知識を教育しても、適切な安全意識が育たなければ、事故を防ぐことは難しいものです。こうした背景の中で、近年、事故抑止効果が高いと注目されているのが、映像による疑似体験です。
映像による疑似体験、特にVR技術などを使って事故の状況をリアルに再現する方法は、その臨場感の高さから注目されています。事故の怖さや危険性を直接的に体感できるため、現場の安全意識を高める上で効果的な教育手法として期待されています。
賛否が分かれるVR
一方で、VRを活用した疑似体験にはいくつかのデメリットも指摘されています。その1つが、コストです。VRコンテンツはリアルでインパクトのある体験を提供する反面、制作費が非常に高額になることが課題です。
さらに、専用デバイスが必要であり、VR体験の利用頻度が制限されてしまう点もデメリットといえます。VR体験を実施するためには、専用のゴーグル等の機器が必要です。しかし、これらのデバイスは十分な数を購入するには高コストな為、多くの企業では、限られたデバイスをシェアしています。
VRによる疑似体験は、その場で強い印象を与えるため、安全意識を高める上で非常に効果的です。しかし、その強いインパクトも時間の経過とともに薄れてしまい「継続的な安全意識の向上にはつながりにくい」と評価されることがあります。
VR体験とは少し異なりますが、皆さん、運転免許更新時の講習で見るビデオを思い出してみてください。運転免許更新時の講習で見せられる事故映像も、視聴直後は強い危機感を与えますが、時間とともにその意識が薄れてしまうことが多いものです。こうした事例からも、安全教育においては「一度強いインパクトを与えれば十分」という考え方ではなく、繰り返しの教育や定期的な意識付けが重要であることが分かります。
持続性を優先した対策
現場の安全教育を進めるうえで重要なポイントは、一度の教育や体験に頼るのではなく、継続的な取り組みを行うことです。どんなにインパクトの強い安全教育を行っても、時間とともにその効果は薄れてしまいます。安全意識を高い状態で維持するためには、教育を繰り返し、継続的な働きかけを行う仕組みづくりが不可欠です。
例えば、高速道路のサービスエリアでは、トイレ前などで事故の映像が流されていることがよくあります。単調な運転で気が緩んでいても、休憩時に大きな事故の映像を見ると「ハッ」として気が引き締まります。
これをヒントに、事業場にモニターを設置して、注意喚起の映像を流し続けるという方法を取り入れると危機感を持続させる効果が期待できます。高速道路のサービスエリアで事故の映像が流れるのと同様に、従業員が日常的に目にすることで、自然と安全意識が高まります。
また、高速道路のように監視カメラがあって、実際の事故が撮影されていれば、その映像を素材として活用できます。しかし、そうでなければCG等で制作できます。実写映像の制作も選択肢として考えられますが、事故の現場を再現するのは非常に難しく、高コストという課題があります。特に、事故の内容によっては、現場での撮影そのものが難しいケースもあります。
例えば、炎が出るような事故を再現する場合、基本的に工場内での撮影が不可能と言って良いのではないでしょうか。
そして、実写の場合は「作り物感」が出てしまうリスクも考慮しなければなりません。映像や演技がいかにも不自然に見えてしまうと、むしろ興味を失わせてしまい、印象に残らないという結果を招きかねません。
一方で、CGアニメーションを使用した場合、実写ほどのリアルさはないものの、視聴者が不思議と受け入れやすいという特徴があります。CGアニメーションは、視覚的な分かりやすさを保ちながら、適度に抽象化された表現で事故の危険性を伝えることができます。(例:図1)
図1:エンジン不停止によるフォークリフト挟まれ事故のCG映像

反対に、リアルすぎる映像は、生々しさが際立ってしまうことがあります。これにより、視聴者が不快感を覚えたり、継続的に視聴するのを嫌がったりする可能性があるため、安全教育の映像としては逆効果になる場合もあります。
作業時に注意すべき手順や、手順を逸脱した場合に想定される事故の映像を制作し、それを事業場内で継続的に流すことで、ふとした時に目に留まり、危機感を持続させる効果が期待できるのではないでしょうか?
映像の作り方を工夫すれば、ナレーションやテロップを入れなくても「非言語」で伝えることが可能です。そのため、外国人労働者にも大きな効果が期待できます。
さらに、モニターの映像は出入りする人全員が目にすることができるため、これを人目の付く場所で流し続けることには「言い訳が効かない状況を作る」という効果もあります。
これは、事故を起こした際に「マニュアルを知らなかった」「忘れていた」あるいは「ちょっとした作業だから大丈夫だと思った」といった言い訳ができなくなるということです。モニターで注意喚起の映像が常時流れている事実そのものが「知らなかった」が通用しないという無言のプレッシャーとして働きます。
労働安全の分野では、単に正しい手順を教えるだけでは不十分です。危機感を伝え、リスクへの意識を高める教育が極めて重要です。これまで繰り返しお伝えしてきたように、安全教育において目指すべきは「ここまでやればOK」という線引きを設けることではありません。常に「事故を起こさない」という根本的な目的を意識し、それを徹底する姿勢が必要です。

執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。