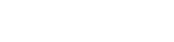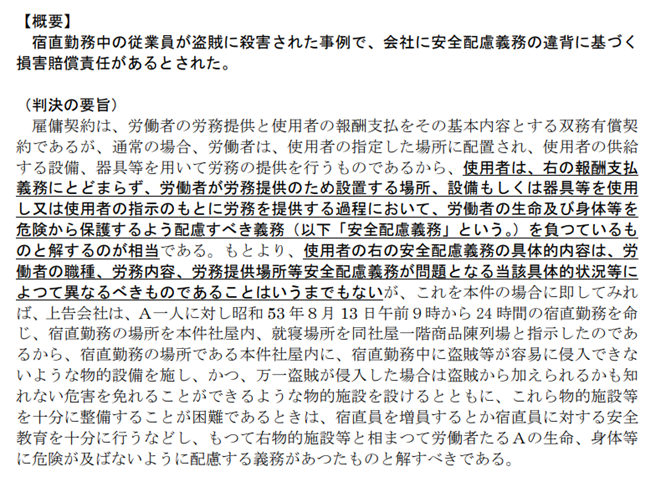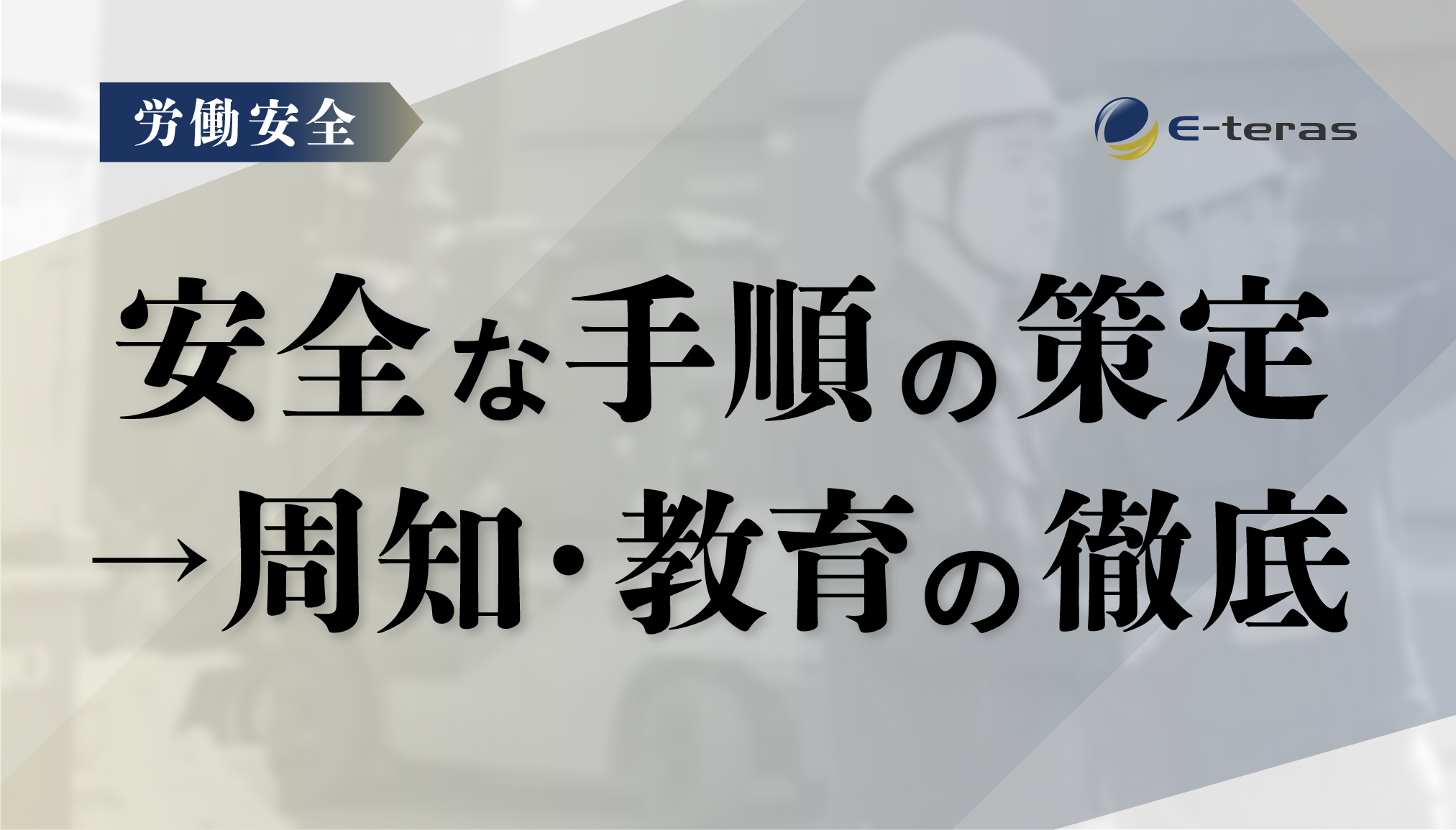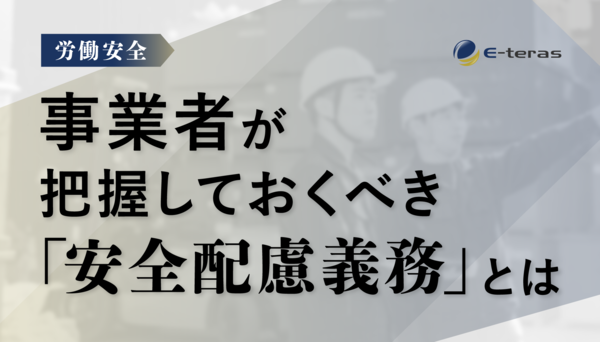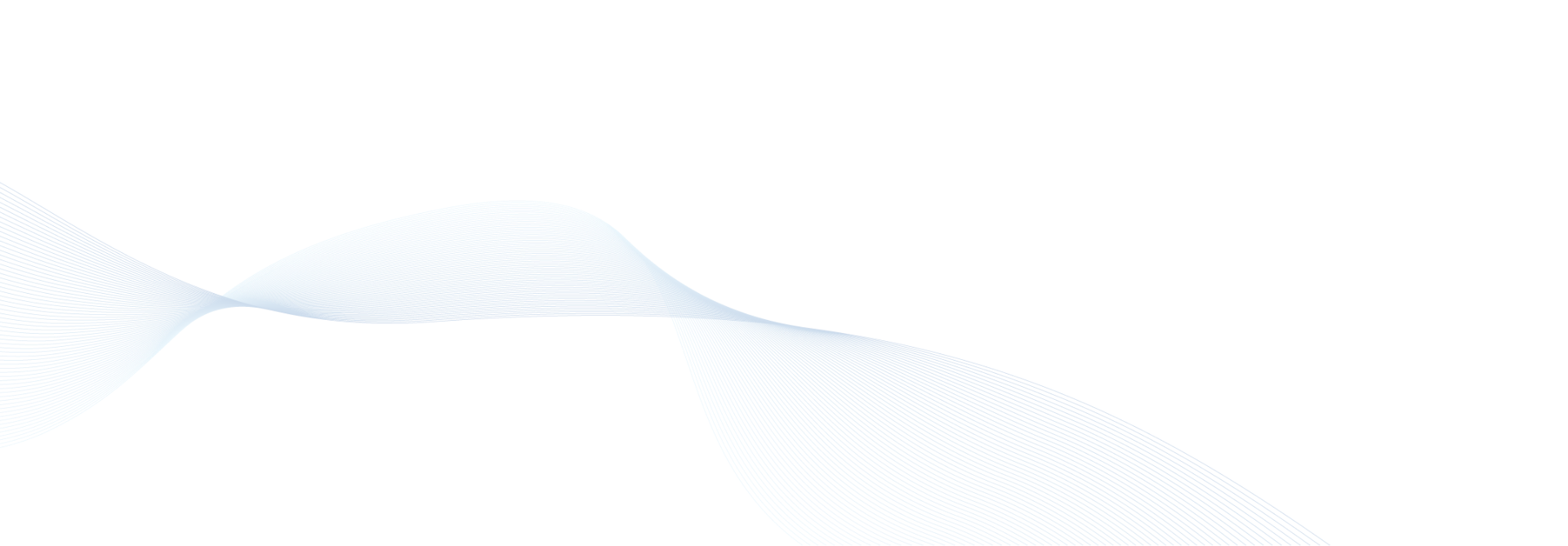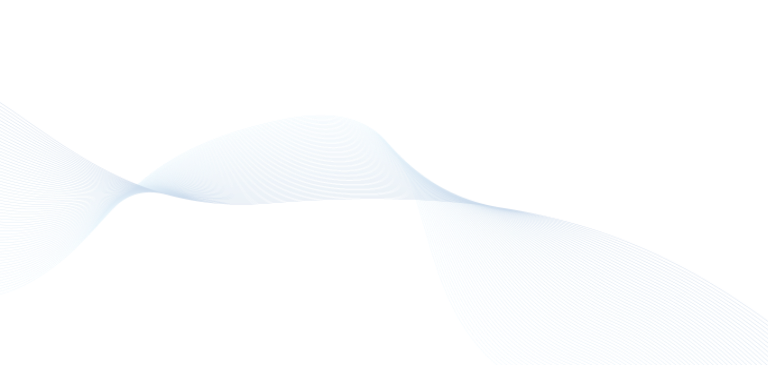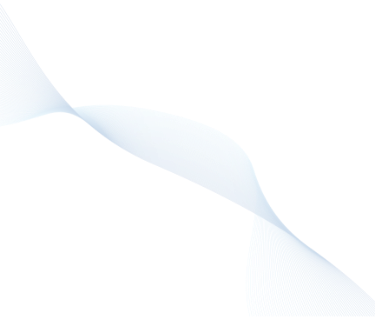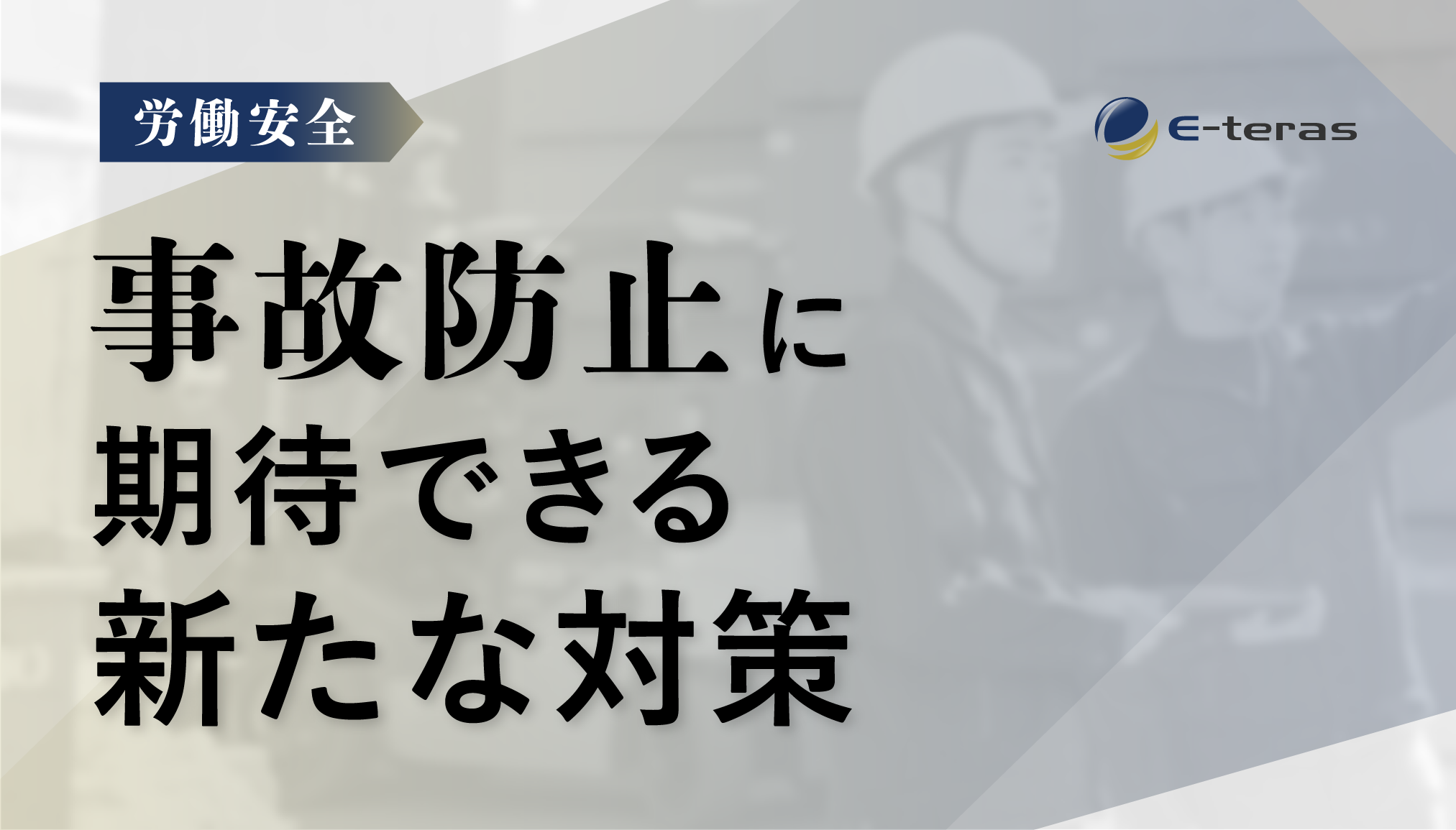



COLUMN
コラム
廃掃法をわかりやすくまとめたり、廃棄物処理業界のDX化の事例をお伝えしています。
廃棄物処理会社様に向けたお役立ちコラムです。
安全配慮義務はケースごとで判断が変わる
コラム『事業者が把握しておくべき『安全配慮義務』とは』で紹介した安全基準はあくまで法律が定める最低限のものであり、実際には事業者が各職場の状況に応じて、より踏み込んだ安全配慮を行う必要があります。しかし、どこまでの措置が必要かはケースごとに異なるため、安全配慮義務には曖昧な部分が残ります。そのため事故が発生した場合、最終的に裁判で、事業者の安全配慮が適切だったかどうかを個別の状況に応じて判断することになります。
衝撃の判例
ここで具体的な事例を紹介します。ある宿直勤務の職員が、勤務中に盗賊から襲撃されるという事件がありました。この事件では、裁判所が「防犯対策が不十分で、施設の安全配慮が足りなかった」として事業者に損害賠償を命じています。このように安全配慮義務は、たとえイレギュラーなケースであっても、事業者に職場の状況に応じた適切な対策を求めていることがわかります。
川義事件(最高裁昭和 59 年4月 10 日第三小法廷判決)
厚生労働省資料:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf?utm
想定外でも責任が
「いや、さすがに盗賊が押し入ってくることまでは想定できないよ」と感じる方もいるかもしれません。しかし、この事例が示すように、安全配慮義務には明確な「これだけやれば十分」という基準がありません。重要なのは、職場ごとに起こりうる危険をさまざまな視点から洗い出し、それに応じた対策を考えることです。また、対策を一度行って終わりではなく、PDCAサイクルを回し継続的に改善していくことが求められます。これは、職場で行われているKY活動と共通する考え方です。
さらに、近年の改正では事業者の安全配慮義務範囲が「労働者」から「作業に従事する者」に拡大されています。
この改正は特化則、有機則などが規制する「有害な作業」については2024年4月、クレーン則、ボイラー則などが規制する「危険な作業」については2025年5月に施行されます。
自ら雇用する事業者のみではなく、下請業者や出入りの業者にも「安全配慮義務」が適用されるのです。
従来の「特化則」や「有機則」は、作業エリアや対象作業者が限定されるため、比較的影響範囲も狭いものでした。しかし、今回の改正により物理的な危険まで対象となったことで、その範囲は一気に拡大しました。具体的にどのような範囲や項目が新たに対象になったかを、以下にまとめてご紹介します。
・危険な場所への立入禁止、特定の場所での喫煙禁止、事故発生時の対処等の対象範囲を「労働者」から「作業に従事する者」に拡大
・「作業に従事する者」は、現場監督や資材の搬入、荷卸しなど、直接作業に関係しない者も含まれる
「クレーン」など、事業場で比較的多くの作業者が出入りするエリアにおいて使用される設備が指定され「資材の搬入、荷卸しなど、直接作業に従事しない者」も対象に含まれるとされています。そのため、結果として安全配慮の対象範囲がかなり広がったことが分かります。
自社の事業場に出入りする作業者は、全面的な対応が必要になるかもしれません。

執筆者
安井 智哉
廃棄物処理会社へ出向し実務経験を積む。現場で得た知識や経験をもとに、お客様の課題に真摯に向き合い最適な提案をおこなうコンサルタントを目指す。
また、静脈産業・廃棄物処理業界の”現場”が抱える課題に着目し、ITシステム等の様々なツールを活用したサービスの開発に努める。